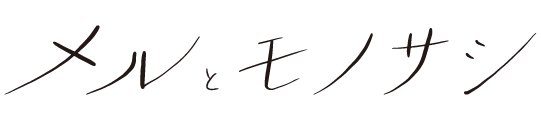2023/12/22 16:46

思い入れはあるけれど、ほとんどつかわないまま、クローゼットに眠っている革製品。多くの人にとって、思い当たるものがあるのではないでしょうか。
バッグブランド「tete」のデザイナー・古田佐和子さんと始まったプロジェクトでは、みなさんから不要な革製品を譲り受け、革と革をつぎ合わせた「エシカルながま口」に生まれ変わらせます。
かつては新品の革をつかって個性的なバッグをつくってきた古田さんが、つかわれなくなった革を生まれ変わらせる「革継ぎ師」として、がま口づくりを始めるようになった背景をうかがうと、デザイナーとしての一貫したスタンスと、これまでのキャリアを経て芽生えた価値観が見えてきました。
制限がある方が面白い
バッグメーカー勤務を経て、東京の若手クリエイター創業支援施設「台東デザイナーズビレッジ」に入居し、2013年に自身のブランド「tete」を立ち上げた古田さん。野菜をモチーフにした個性的なバッグをデザインし、はじめは国内、やがてバングラデシュの工場に発注する形で商品をつくってきました。

バングラデシュの工場に発注するときはオリジナルの革をつくらず、現地で調達できる他のメーカーのストックから革を選び、バッグをデザインしていたそう。限りある中から素材を選んでデザインするというやり方は、クリエイターにとって窮屈なのでは?と疑問が湧きますが、古田さんはそこに面白みを感じていたといいます。
「コストをかけてオリジナルの革をつくることもできるけど、デザインするってそういうことじゃないだろうって、ちょっと思ってたんですよね。逆に制限の中で、あるものだけをつかっていかにオリジナリティを出すか、というのが面白くて。今思えば、その頃から“エシカル”につながる思いがあったのかな」
ファスナーなどの副資材も同様に、入手できる範囲のものを選び、つかっていたそう。イメージとは少し違ったものでも「つかい方次第でいい感じになるんだなって学びましたね」と振り返ります。
誰のためのものづくり?
台東デザイナーズビレッジでたくさんのクリエイターに囲まれ、刺激的なブランド立ち上げ期を過ごしたあとは、地元・横浜のシェアオフィスに入居し、バングラデシュで生産したバッグを百貨店催事やオンラインショップで販売するスタイルで活動。同じオフィスでは、NPOなどの社会貢献事業に関わる人が多く働いていました。
「まちづくりや福祉に携わる人が多い中、私だけメーカーで、一人だけ毛色が違ったんです。貧しい国の人のためにとか、商店街に活気を取り戻そうとか、誰かのために一生懸命やっている人を見ていたら『つくりたいものをつくって売るって、誰のためになっているんだろう』って自分の仕事に疑問を感じ始めてしまったんです」

明確な答えは出ないまま、出産を機にシェアオフィスを退去。育児に追われる日々を過ごす中、新型コロナウイルスの世界的パンデミックが訪れました。百貨店催事での販売は難しくなり、古田さんは生活のために飲食店でパート勤めをすることに。料理人である夫の三浦さんも大きな打撃を受け、夫婦で仕事へのやりがいを感じにくい状況が続いたといいます。
そこで、新規事業として夫婦で始めたのがteteのショップ&カフェ「tete cafe」です。古田さんがオーナー、三浦さんがシェフとなり、2021年5月に横浜市青葉区にオープンしました。teteのバッグを展示・販売するとともに、三浦さんによるカジュアルフレンチを提供するお店として、忙しい日々を送ることとなりました。

デザインや革のあり方を再考
慣れないカフェ業務と子育てに追われ、なかなかバッグの製作を再開できずにいた古田さん。過去につくったバッグを売るだけの日々でしたが、子どもが成長し生活が落ち着いてきたこともあり製作を再開しようと考えたときに、 “デザイン”そして“革”のあり方と改めて向き合ったといいます。
「デザイン学校時代、無駄なものをつくるとごみを増やすことになるんだ、って何度も話してくれた先生がいたんです。たとえば丸い壁の建物は家具が置きにくいなど、デザインを重視しすぎてつかい勝手を考えないものは価値が下がり、無駄になる。『デザインってごみを増やすことにもつながってしまうんだな』って、ずっと心の底にあったんですよね」
過去の製作スタイルはこの考えがあってこそ。これをさらに加速させたのが、飲食業を営む中で得た、動物由来のものを避ける“プラントベース”の人が増えていることへの気づきでした。
「家畜から二酸化炭素がいっぱい出るから環境によくないとか、そういう話を聞く中で、革製品をつくるのは時代に反している気がして。でも、革は素材としてはとても魅力的なものだから、何か違うアプローチでものづくりができないかなと思って。それで、新しい革を購入するんじゃなくて、もうすでに世の中に出ている革を再利用するような形でつくれたらいいなと」

それを一番シンプルな形で実現すべく、デッドストックの革や不要になった革製品をそのまま活用する方法を模索しました。以前はフリーマーケットによく足を運んでいたという古田さんは「人が愛着を持っていたものが、違う人のものになるって、なんか面白い」と語ります。もともと、ものを循環させていくしくみに興味があったのです。

女性の自信につながるものを
いざバッグを製作しようとアイデアを練る中で、浮かんできたコンセプトは「子育てしながら働く女性を応援したい」というものでした。
「女性の自信につながるようなバッグにしたい、とざっくり考えていて。やっぱり子育ても仕事もするって大変じゃないですか。その思いに寄り添えるようなものをつくりたいと思ったんです」
新しい商品の試作を始めたものの、思うようにはいかず試行錯誤の繰り返し。最終的にがま口に行き着いた大きな理由は、その“つくり方”にありました。小物ながら、古田さんがつかうバッグ用ミシンでも縫製可能なシンプルな構造と、職人でなくても口金を取り付けやすいということ。ここに、がま口の可能性を見出したのです。

「いろんな人に体験してもらうとか、一緒につくるっていうことにつなげやすいんですよね。私はミシンで革を縫っているので、これまではワークショップができなかったんです。がま口なら、革を縫うところは私がやって、最後に口金で挟む工程をみなさんに楽しんでもらえる。そういうのをやりたかったし、将来的に量産することになったときに、お仕事を探している主婦さんにお願いできたらいいなというのもあって」
古田さん自身がパートで働くことを選んだとき、子育てしながら職を探すことの難しさを体感しています。だからこそ描けた、女性の“働く”までを見据えたものづくりのしくみ。「シェアオフィスでNPOの人たちに出会った影響が大きい」と振り返るように、当時感じていた葛藤をも消化してくれます。
異なる素材感の革がなじむ
エシカルながま口のプロジェクトは、まだ始まったばかり。最初は古田さんがかつてオーダーメイドでバッグづくりをしていた頃に仕入れた革のストックをつかった商品が中心ですが、今後、つかわれなくなった革製品を素材にしていくことで、いろいろな表情のものが生まれていく予定です。
「革って質感や厚みがバラバラで、素材感が全然違うんだけど、組み合わせたら不思議となじんで全体がまとまって、違いが気にならなくなるんですね。これはつくってみて初めてわかりました。そうやって全然違う革どうしが一緒になったとき、いとおしさが湧いてくるんです。それこそが革の魅力ですよね。今後、すでに味のある革でつくるようになったら、もっと面白いものができるんじゃないかな」

「tete cafe」で開催しているワークショップはとても好評だそう。メルとモノサシへも、本革製品を持ってきてくださる方が少しずつ増えてきました。自分でつくったものや、自分の革製品が生まれ変わってできたものは、大事につかい続けたくなることでしょう。人びとが何らかの形でものづくりに関われるこのプロジェクトは、素材を循環させるだけでなく、つかい手の愛着をも育むはずです。
「限られた素材で面白いものをつくる」という古田さんのゆるがないスタンスに感心するとともに、無限に広がるその“いかし方”の可能性に面白さを感じずにはいられません。

Sawako Furuta
1982年生まれ。桑沢デザイン研究所プロダクト科卒業。バッグメーカー勤務後、2013年台東デザイナーズビレッジ入居をきっかけにバッグブランド「tete」を設立。2014年より単身バングラデシュでの生産を開始しデザインから輸入卸をすべて一人で行い、年間15回、全国の百貨店でポップアップを中心にオリジナルデザインのバッグを販売。出産を機に2021年、フレンチシェフの夫とカジュアルフレンチとバッグのお店「tete cafe」をオープン。バングラデシュでの生産とパンデミクスをきっかけに「革継師」という肩書きで、新しい革を使わず既に世に出ている革の継ぎ接ぎでものづくりする、シンプルなものづくり活動で手づくりバッグを再開。